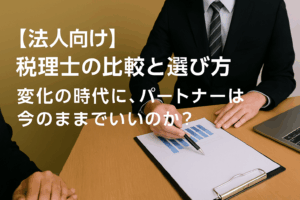【大阪】税理士顧問料の相場はいくら?料金の目安と費用対効果を徹底解説
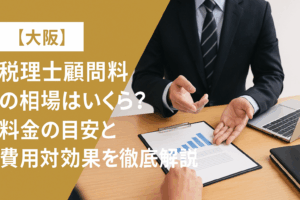
・大阪での税理士の料金っていくらが妥当なのか知りたい
・今お願いしている税理士の料金が高い気がするけど、内容とのバランスが分からない
・これから税理士を選ぶけれど、失敗したくない
そんなお悩みや疑問をお持ちの方に向けて、この記事では法人向けの税理士顧問料と決算料の相場に加え、
・顧問料が高い・安いの判断軸
・サービス内容の違いと本当に見るべきポイント
・成果を出す税理士の選び方
・税理士を切り替えるタイミングと注意点
まで、実際の事例やプロの視点も交えて詳しく解説します。
読み終えたときには、「安さだけで選ばない」視点が自然と身につき、自社に合った“本当に頼れる税理士”を見つける判断力が手に入ります。
法人の大阪での税理士顧問料の相場とは?
・売上(年商)
・会社の規模や業種の特性
・面談の頻度
・経理処理の範囲
・税理士がどこまで関与するか
によって、料金は大きく変わるからです。
以下はあくまで一例ですが、参考として一般的な法人向け顧問料の目安を整理してみました。
| 年商規模 | 年1回面談 | 3ヶ月ごと面談 | 毎月面談 |
| 〜1,000万円 | 5,000〜15,000円 | 15,000〜25,000円 | 25,000〜40,000円 |
| 1,000万〜3,000万円 | 10,000〜20,000円 | 20,000〜35,000円 | 35,000〜50,000円 |
| 3,000万〜5,000万円 | 15,000〜25,000円 | 30,000〜50,000円 | 50,000〜70,000円 |
| 5,000万〜1億円 | 20,000〜35,000円 | 40,000〜60,000円 | 60,000〜90,000円 |
| 1億円〜3億円 | 30,000〜50,000円 | 60,000〜90,000円 | 90,000〜150,000円 |
もちろん、この金額は単なる「目安」にすぎません。 実際の契約では、記帳代行の有無や面談の密度、税務相談の範囲などによって料金に幅があります。
重要なのは、「何に対してその金額を払っているのか」を把握していることです。
特に月額3万円〜5万円程度の顧問料帯では、税理士が「帳簿をつけるだけ」なのか「経営を一緒に考えてくれるのか」で、費用対効果は何倍にも差が開きます。顧問料は単なるコストではなく、**経営の意思決定を支えるための“投資”**として捉えることが重要です。
大阪での決算料の相場は?
顧問契約をしていても、年に1回の決算・法人税申告には別途「決算料」がかかることが一般的です。 これは、
・決算書の作成(貸借対照表・損益計算書)
・税務申告書の作成
・税務判断の確認と調整
・税務署への申告提出代行
といった業務が一括して含まれるためです。
| 年商規模 | 決算料の目安 |
| 〜1,000万円 | 50,000〜100,000円 |
| 1,000万〜3,000万円 | 100,000〜150,000円 |
| 3,000万〜5,000万円 | 150,000〜200,000円 |
| 5,000万〜1億円 | 200,000〜300,000円 |
| 1億円以上 | 300,000円〜 応相談 |
決算料が高い・安いというよりも、「何が含まれているのか」「どれだけの品質で提供してもらえるのか」がポイントになります。
たとえば、単に税務申告を済ませるだけの決算と、節税の選択肢や金融機関への説明を意識した決算では、その経営インパクトはまったく異なります。
特に資金調達や節税を意識する中小企業にとっては、“申告して終わり”ではない付加価値のある決算サポートが、経営の強力な支えとなるのです。
顧問料が変動する2つの理由:売上規模と面談頻度
大阪での税理士顧問料の相場を見て「高い」「安い」と感じることはあるかもしれませんが、大切なのは“なぜその金額なのか”という背景を理解することです。
① 売上規模が大きくなると、税務対応の範囲も広がる
会社の売上が大きくなればなるほど、取引数が増え、帳簿付けの量や税務判断の複雑さも増します。資産の管理、在庫処理、貸倒引当金、役員報酬、交際費、減価償却など、一定規模を超えた会社にはより高度な処理が必要になります。
当然、税理士が確認すべき項目やリスクも増えるため、それに応じて顧問料も上がっていきます。
② 面談頻度が高いと、伴走支援型の関与になる
「年1回決算の報告だけ」と「毎月数字を見ながら経営の改善を話す」のでは、税理士の役割も大きく異なります。
・数字の読み方を説明してくれる
・資金繰りや利益率の改善アドバイスをくれる
・人件費の構成や経費バランスの見直しを提案してくれる
など、面談の頻度が高くなるほど、より深い経営支援が受けられるようになります。こうした“月次伴走型”の支援は、確かに顧問料は高くなりますが、その分得られるリターンも大きいのです。
税理士の本当の価値は「決算前の意思決定支援」にある
「節税対策がしたい」「利益をコントロールしたい」
そのような要望を税理士に伝えても、決算が終わってからでは基本的に手遅れです。真の意味で節税や利益対策を実現するには、「事前に数字を把握し、手を打つ」必要があります。
決算の3か月前からが勝負の分かれ目
・着地見込み(予測損益)の確認
・必要に応じた経費の調整
・資金繰りと納税資金の確保
・節税対策の選択肢(設備投資、保険活用、繰延など)
これらはすべて「決算前に相談し、動く」からこそ意味があるのです。
実際、決算前に適切なアドバイスをもらえれば、税額が数十万円〜数百万円単位で変わることもざらにあります。
つまり、税理士の真価は「帳簿をつける人」ではなく、「数字から経営判断をサポートしてくれる人」なのです。
顧問契約に含まれるサービス内容の違い
顧問契約を結んでいても、税理士事務所によって対応範囲は大きく異なります。以下の表は一例です。
| サービス内容 | 内容の範囲 | 支援の深さ |
| 記帳代行 | 領収書・通帳などから仕訳入力 | 非常に限定的(事務代行) |
| 試算表作成 | 月次の数字をまとめて報告 | 表面的な確認までが多い |
| 月次決算・面談 | 経営数値の分析+課題抽出 | 経営支援がスタートするレベル |
| 予実管理+事業計画支援 | 計画作成・PDCAの伴走支援 | 高度な経営改善・成長支援 |
同じ“顧問契約”でも、これだけ中身が違うのです。
「顧問料が安い=得」ではなく、**サービスの中身に対して妥当な金額か?**が大切な判断基準になります。
【大阪府内】地域別・税理士顧問料の相場比較
大阪と一口に言っても、中央区や北区の都市部エリアと、東大阪や堺などの郊外・工業地域では、顧問料の相場感に違いが出るのが実情です。
たとえば…
✅【大阪市内(中央区・北区・西区など)】
・上場準備企業やIT・不動産業が多く、会計の高度化が求められる傾向あり。
・顧問料は月3万〜6万円がボリュームゾーン。
・自計化やクラウド会計に強い事務所が多く、効率的な分単価は低めでも付加価値が高い。
✅【東大阪・八尾エリア(製造業が集まる地域)】
・製造原価計算や棚卸、減価償却など複雑な処理が多いため、顧問料はやや高め。
・月4万円〜7万円前後が一般的。
✅【堺市・岸和田市などの南大阪エリア】
・建設業・医療法人・サービス業など、地域密着型ビジネスが中心。
・月2.5万円〜4万円程度で、訪問頻度よりもコスト重視のニーズが目立ちます。
✅【豊中市・吹田市など北摂エリア】
・医療・教育・士業などが多く、クラウド会計導入率も高い。
・顧問料は月3万円〜5万円、オンライン面談・レポート重視の傾向があります。
地域ごとにこんなに違う!エリア別相場まとめ(一覧表)
| 地域 | 主な業種 | 月額顧問料の目安 | 傾向/特徴 |
| 大阪市内(中央区など) | IT・不動産・スタートアップ | 3万〜6万円 | クラウド対応・オンライン面談・高付加価値支援 |
| 東大阪・八尾 | 製造業(部品、金属加工など) | 4万〜7万円 | 税務処理が複雑・訪問頻度高・業種特化ニーズ |
| 堺・岸和田(南大阪) | 建設・医療・小売 | 2.5万〜4万円 | 地域密着型・価格重視・訪問型スタイル |
| 豊中・吹田(北摂エリア) | 教育・医療・不動産・士業 | 3万〜5万円 | デジタル活用・レポート分析・オンライン対応が主流 |
「大阪で税理士を探す」といっても、エリアによって提供スタイルも価格感も大きく変わります。
安さだけでなく、「業種に合った支援ができるか」「クラウドに対応しているか」などを見極めて選ぶことが、成果につながる税理士選びのカギです。
税理士事務所によって変わる「付加価値」の差
税理士の本当の違いは、「帳簿をつける」その先にあります。近年は会計ソフトの進化により、記帳や試算表の作成といった作業は多くの事務所で標準化されています。
しかし、「その数字をどう経営に活かすか」まで考え、支援できるかどうかは、税理士ごとに大きな差が出る部分です。
税理士事務所によって対応できる“付加価値業務”の例
・銀行融資の相談や、金融機関との面談同行
・補助金・助成金の情報提供と申請支援
・給与制度・評価制度の構築支援
・社会保険や労務管理の課題への対応(社労士連携)
・契約書のレビューや法務トラブルの初期対応(弁護士連携)
・M&Aや事業承継の初期支援
・商標・特許など知的財産の相談や申請サポート(弁理士連携)
このように、税理士が経営全体を見渡し、他士業と連携してワンストップで支援できるかどうかが、税理士選びの重要なポイントです。
経理体制の構築も、税理士によって全く変わる
経営者の多くが「もっと経理を効率化したい」「経理担当に依存しすぎていて不安」と感じています。
そんなときこそ、DX(デジタル化)・ITに強い税理士事務所の存在が非常に重要です。
経理改善で得られるメリット
・クラウド会計ソフト導入で業務が大幅に自動化される
・銀行・クレジットカード・請求書システムとのデータ連携で記帳が不要に
・請求書・領収書のペーパーレス化で紙処理を削減
・担当者の退職や引き継ぎにも強い「仕組み化」された経理体制
これにより、経理担当の作業時間が月10〜20時間削減できたケースもあり、月額数万円相当のコストカットにつながる例もあります。
経理は単なる裏方業務ではなく、「効率化=利益アップ」に直結する分野です。だからこそ、仕組み化の支援ができる税理士を選ぶことが経営改善の第一歩になるのです。
税理士を変えるタイミングと注意点
「今の税理士に不満はあるけど、変えるのは手間がかかりそう…」と感じる方も多いのではないでしょうか?
実は、今は税理士の切り替えハードルが大きく下がっている時代です。
会計ソフトの進化で「期中の変更」もスムーズ
・クラウド会計を使っていれば、仕訳データや残高も簡単に移行できる
・書類のやりとりもデジタル化され、やりとりの手間も軽減
・新しい税理士が前任の税理士との引き継ぎをリードしてくれるケースも多い
決算期の前後にかかわらず、「今が変えるべきタイミング」であることも少なくありません。
今後の経営に大きな影響を与える税理士の存在を、“なんとなくの付き合い”で続けるのは非常にもったいないことです。
まとめ:「安さ」より「成果」で選ぶ税理士
税理士の顧問料は、確かに月額で見れば数万円の差があるかもしれません。
でも、その差額以上に“成果”が違えば、むしろ高い顧問料の方が得をするというケースは多々あります。
たとえば、こんな成果が出るなら…
・決算前の利益調整で納税額が100万円下がった
・資金繰り改善の助言で倒産の危機を回避できた
・経理業務が仕組み化され、年間200時間の削減に成功
・融資資料の整備で数千万円の資金調達がスムーズに進んだ
このように、「安さ」に目を向けすぎることで、本来得られたはずの大きな“経済的価値”を逃してしまっている企業は少なくありません。
顧問料=コストではなく、“経営に貢献する投資”と捉えて選ぶ。
これが、今の時代の“成果を出す経営者”が実践している税理士選びの基準です。
ご相談はこちらから
「数字を整理してもらうだけではなく、経営に活かす税理士と出会いたい」 「今の事務所では限界を感じている」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。