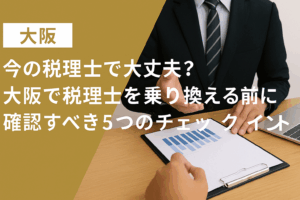【法人向け】税理士の比較と選び方|変化の時代に、パートナーは今のままでいいのか?
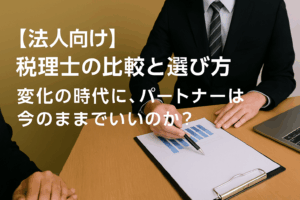
はじめに:税理士を比較するという選択肢
法人経営をしていると、日々の業務、資金繰り、人の問題など、経営課題は尽きません。そんななかで、**経営の数字やお金に向き合う支援者としての「税理士」**はどんな立ち位置にいるでしょうか。
「何となく毎月のやり取りがルーティン化している」
「提案というより、処理だけされているように感じる」
そんな違和感があっても、見直すきっかけがなく、**“なんとなく続いている関係”**になっていることも。
この記事では、法人が税理士を見直す際に役立つ比較ポイントと、判断の軸を整理します。
派手な変化や対立ではなく、納得感のある判断をするための視点をお届けします。
1. こんな兆しがあれば、税理士比較のタイミングかもしれません
以下のような状態が続いている場合は、いったん現状を見直す価値があります。
・数字の報告が一方通行で、説明や背景がない
・決算が近づくまで税金や利益の話が出てこない
・担当者が変わるたびに業務の抜け漏れがある
・クラウド会計に変えたのに、効率化されていない
・顧問料に対して、支援内容に差があると感じる
「不満があるわけではない。でも物足りない」
これは、企業が成長している証拠でもあります。成長段階に合わせて、支援体制やパートナーの役割も変わって当然です。
2. 法人が税理士を比較するときの主要な視点
① サービスの「内容」と「深さ」
税理士の仕事は記帳・申告にとどまらず、本来は経営に寄り添う役割もあります。
例えば以下のような対応に違いが出ます。
・毎月の数値変化をどう伝えてくれるか
・利益・資金繰りへのアドバイスがあるか
・計画や投資判断について意見をくれるか
数字が“出てくる”だけでなく、“読まれて、使われている”かを見てみましょう。
② ツール活用とデータ整備の仕組み
会計ソフトがクラウド化されても、入力・証憑整理・月次報告は属人的なままという事務所もあります。
・freee・マネーフォワードなどの操作支援
・領収書読取ツール(Streamed等)との連携
・会計データを経営レポートに整形する仕組み
単に「クラウドに対応している」だけでなく、現場が実際にどう運用しているかに注目するのがコツです。
③ 担当者の関わり方と継続性
税理士の担当者が変わったり、経験が浅いままだと、会社側の負担は増えがちです。
・担当が定期的に変わるかどうか
・経営者と「会話」になるか
・数値に基づいた提案があるか
関わりの深さは、単なる応対ではなく、経営にどう向き合っているかで見えてきます。
④ 組織体制と対応範囲の広さ
小規模事務所では柔軟な対応力が魅力ですが、成長企業にとっては対応漏れやリスクヘッジの面で限界が出ることもあります。
・品質管理やダブルチェック体制
・労務・資金調達・事業承継などの周辺支援
・データ連携や定型業務の自動化設計
こうした面まで整っていれば、経理や財務の基盤が「仕組み」として整備されていきます。
3. 比較の視点を“価格”から“価値”に
顧問料が高いか安いかというよりも、「その金額で何が得られるか?」に目を向けてみましょう。
| 顧問料 | サービス例 |
| 月2万円 | 記帳+申告、問い合わせ対応 |
| 月5万円 | 月次レポート+決算対策+年1〜2回相談 |
| 月8万円〜 | 月次ミーティング+経営課題分析+AIを活用した数値アラート設計 |
これは一例ですが、料金の背景にある「関わり方」や「考え方」に注目すると、本質的な違いが見えてきます。
4. 成長ステージごとの適した税理士像
| ステージ | 合う税理士の特徴 |
| 創業〜年商3000万円 | シンプルに記帳+申告を正確に対応 |
| 3000万円〜1億円 | クラウド活用+数値の月次報告あり |
| 1億円〜3億円 | 経営に関わる視点での月次支援・資金繰り助言 |
| 3億円以上 | 組織対応・人材確保・事業計画と連動した支援 |
事業規模が変われば、求められる役割も変わって当然です。
「税理士は変えないもの」という思い込みを、一度外してみてもよいかもしれません。
5. 税理士変更の現実的な流れ
・変更時期は決算後 or 新期がベスト
・現在の契約条件を確認(〇ヶ月前通知など)
・決算書・仕訳帳・申告データの受領
・新税理士との役割確認とデータ共有
変更には一定の労力がかかりますが、中長期的に得られる安心感や、経営判断の質の向上は大きなリターンです。
おわりに:「見直す=対立」ではない
今の税理士が悪いわけではない。
ただ、**今のステージの会社にとって合っているか?**を見直すことは、健全な経営判断のひとつです。比較し、検討し、納得して選ぶ。
その過程は、経営者にとって「数字を使って未来を考える」トレーニングにもなります。